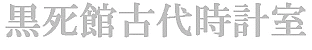素天堂ふるほん噺(その1)
★前(プレ)古本屋時代
子供の頃から本が好きで、小学校の図書室はほとんど読み尽くし、雑誌は買ってもらえないので、駅裏に出没する露天商の月遅れ雑誌や付録をたまに買っていたのが小学校時代中期まで。
貸本屋さんが地元の街にもできて(本業は炭屋さんだった)百円貯まると、当時貸本でしか読むことのできなかった手塚治虫の旧作や当時勃興してきた「X」や「影」などの貸本漫画を、家にもって帰れなかったのでその家の濡れ縁で十冊まとめて借りたものを半日かけて読みふけったものだ。もちろん上得意だったから、店番のおかーさんの2〜3冊おまけのサービスがあったりした。
さらに上級生から公立図書館の存在を教わったのは、5年生くらいだったろうか。米軍払い下げのカマボコ兵舎を改造した地元の図書館は、当時の少年には多分夢の世界だったのだと思う。
一番近い盛り場の渋谷駅前にプラネタリウムがあって、そこのショウケースで創刊されたばかりの「SFマガジン」を見つけたのもその頃だった。写真やモデル像がほとんどだった雑誌の表紙が中島正侃の抽象画だったのが印象的だった。
その頃の小学生はまだ、ポケット・ミステリーやSFシリーズを知らなかったから、小学校の図書館の空想科学小説(石泉社のものや講談社のシリーズですね)や冒険小説(当時の認識では講談社版の世界名作全集はそうだった)を大人が読むのにビックリしたのかもしれない。
その当時、新聞配達は子供にできる、唯一のアルバイトだったので伝手をたどって、お金を稼ぐようになった。家にも入れてはいたが、自分の自由になるお金ができて最初に定期購読したのが「SFマガジン」だった。表紙どころか別刷りページもなくなったその頃の現物は今でも手元にある。フレデリック・ブラウンの「狂った星座」レイ・ブラッドベリの「イカロス・モンゴルフィエ・ライト」R・Aハインラインの「輪廻の蛇」ジャック・フィニイ「地下三階」そしてダニエル・キイス「アルジャーノンに花束を」。これらは多分、今に至るも自己ベストだと思う。こんな世界を知った小学生が奇妙な世界に狂ってしまうのは当然だろう。
さらに、新聞配達は別の副産物も自分に用意していた。
一軒のお客の窓際に本棚があってそこには、当時揃ったばかりの桃源社版(四六判ボール箱入り)があって、新聞配達の少年を誘惑した。
当然、本好きの小学生の定番「少年探偵シリーズ」を読みふけったことのある少年は、乱歩に過剰反応した。多分自分で読んでいたからわかっていたのだと今にして思うが、その家のおかーさんは一応は反対した。「子供が読むにはまだ早い」と。そんな制止を振り切って、無謀にも大人の乱歩に挑戦したその子には、幸いなことにまだ読解力がなかったから、勝手に自分の中でリライトしてしまっていた。とはいえ、そこから、探偵小説が大人の世界にもあることがわかったその少年はもう一つの悪の道に迷い込むことになった。「パノラマ島奇談」や「猟奇の果て」「陰獣」etc。でも面白かったんだろうなあと思う。ずっと後になって高校生になった頃、また読み返したくなった時には何期目かの乱歩不遇時代で、新刊書店では新潮文庫版の白帯の「傑作選」くらいしか買えなくなっていた。
そう言えば今年の夏の必読書にまた「江戸川乱歩傑作選」が入っていたっけ。約40年の月日がたっても乱歩へのイニシエーションは新潮文庫なんだなぁ。他の版の全集が手に入りにくい状況までがそっくりだ。
卒業までにほとんどの本を読み尽くしたに等しい小学校の図書室に別れを告げると、その数倍の規模をもった中学校の図書室が待っていた。
世界大ロマン全集(カー「髑髏城」ピエール・ルイス「ポーゾール王の冒険」ストーカー「魔人ドラキュラ」フィシェ兄弟のユーモア・コント集や乱歩や平井呈一の怪奇小説のアンソロジー、そうだケストナー「消え失せた密画」や「雪の中の三人男」もそれで読んだんじゃないか?)、宮沢賢治全集、世界ユーモア全集(カミ「エッフェル塔の潜水夫」エイメ「マルタン君物語」ウッドハウス「マリナー氏御紹介」)を始めとするさらなる鉱脈は、幻想・ファンタジイ・ユーモア小説へとその少年を誘い、書店で「ヒッチコック・マガジン」や「宝石」に手を出す悪い子に成長した。
そんな中学生の火口に油を注いでくれたのは、1年当時の生物の教師で、少年の担任であった某先生。ある放課後、愛車であったラビット・スクーターの後部に本好きな教え子を載せ(←人を乗せるところではない筈だから)、国道246号を二子橋を渡って、さらに瀬田のおおきな坂を登っていった。
地獄の釜は大山街道沿いの三軒茶屋で口を開けていた。駅前の小さくて暗い本屋しか知らなかった彼は、明るい照明と広い店内、高い天井までつづく書棚一杯に詰め込まれた膨大な書籍の量(もちろんそのときの少年の思いこみである)は初めてはいった古本屋という世界に一瞬にして取り込まれたのであった。それが三茶書房の初体験だった。
じつは、彼にはちょっと前に古本屋体験はあった。
公立図書館を教えてくれた上級生が中学に入学した後だったが、少年を神田という街に誘った。なぜかというと彼はどこからか当時の発禁本のリストを手に入れており、そう言う本を買うには神田という街に一杯本屋さんがあって、そこに行けば買えるらしいというのだった。そのうちの一冊が「肉蒲団」という題名だったことは覚えている。もっともどこへ行けば買えるという本屋の情報を、彼はもっていなかったと思う。
初めてでもあり、一人では心細いという上級生の、一緒に来てくれたら何か一冊買ってくれるという甘言に乗せられて、どういう経路を辿ったのか神保町の地獄巡りをしたのだが、実際には記憶がほとんどない。もちろん文庫で買える今と違って、当時どこの本屋でも表にそんな本を出している店があるはずもなく、聞くわけにもいかないで上級生本人は多分なにも買わずに来たのではないか。しかも帰りの電車賃が足りず、当時地上駅だった某私鉄某駅のホームの最後尾から飛び降りて逃げ帰ったのははっきり覚えている(終点の駅では改札を通らなければでられなかった)。
ただ自分は、約束だった一冊として、多分「アメージング・ストーリー」かなにかのSF関係の洋雑誌のバックナンバーを買ってもらった。なにしろ、表紙を見ればその手の雑誌だとすぐ解るものだったから。読めるはずもないその洋雑誌は当時知り合いだったある大学生に、読んでもらおうと思って貸したっきり戻ってこなかった。大学生なら英語がわかるなんて、幻想だったのだ。今なら、分かり切ったことなのにね。結局いい思い出は初体験にはなかったのだ。よくある話だが。
最初のうち三茶書房での買い物は当時興味の中心だった自動車関係のバックナンバーだったが、とにかく平台に山と積まれたバックナンバーと店中を埋め尽くす本の棚に圧倒されながら、徐々に古本屋のよさを満喫するようになっていた。
並行して精勤していた公立図書館(なにしろ三年間、週に1,2回は学校をさぼって町の図書館に通学していたのだから。今思えばあの図書館の司書さんはよく学校へ通報しなかったものだ。それどころか冬の朝などは開館前に入れてくれて、事務所のダルマストーブに当たらせてくれたのだから、ありがたかった。まあシステマティックになった今の図書館では考えられないけれど。)では、大判の河出書房版の現代西洋美術の画集や、これも河出版のピンクや空色のクロス装だった世界文学全集に手を出すようになっていた。
シュルリアリズムの奇妙な作品群に引きずり込まれたり、小学校で読んでいた講談社版「厳窟王」と全訳版「モンテ・クリスト伯爵」(河出版全集だった)の違いに目を見張ったのはそのときだった。巧妙にアレンジが施され短縮された、ファリア神父との衝撃的出会いから始まる「厳窟王」と、ファラオン号の到着からゆっくりと始まる雄大な原作は、最初はまったく違うもののように思われたものだ。もちろんダンテス逮捕のシーンからは物語に入りこんでしまい、その作品は以後彼の最良の愛読書になった。版は岩波文庫に変わったが。
探偵小説と言えばホームズ、乱歩、精々が出始めた松本清張(知り合いのお姉さんが教えてくれた)だった少年に今で言うカルチャー・ショックを与えてくれた本に出逢ったのも公立図書館だった。その作品は都筑道夫「やぶにらみの時計」。中央公論社から出版されたその本は、全面を黄色い艶のあるコート紙に、真鍋博のゆがんだ柱時計のイラストが小さくあしらわれた表紙で包まれていた。いまでもドキドキするような挑発的な装幀だったとおもう。挑戦的であったのは装幀ばかりではなかった。二人称で叙述される奇妙な事件は、少年にまったく新しいミステリーの世界を教えてくれた。
とはいえその水準の作品がそこら中にあるはずもなく、新潮文庫の白帯で、翻訳物の古典を探したり角川文庫で、幻想系の外国文学をほそぼそと読むことになる。巻末のリストにありながら、駅前の暗い小さな本屋さんで注文すると、大概は品切れ絶版という悲しい思いを繰り返したのがその頃の中学生の読書事情だった。その駅前の本屋さんが、今では関東地区で悪名高きロードサイド書店の雄「文教堂」の前身だったのだから、わからないものだ。
その公立図書館にはさらに戦後の米国進駐軍からの寄贈か貸与だったのだと思うが、一角に米国書のコーナーがあってどんなチョイスなのか、ハードカバーのチャールズ・アダムズの画集や、フレドリック・ブラウンの短編集のペーパーバックなどがあった。また写真年鑑で当時のアメリカ車を嫌というほど見せられて、アメリカはいい国・キャンペーンはその頃の車好き、本好きの中学生には、それは予期せぬ形ではあれ、米軍の思惑通りの効果をもたらしたのかもしれない。
小学校時代が学校の図書室と貸本屋の時代だったとしたら、中学校時代は、町の公立図書館主体の、自分にとってまだ前(プレ)古本屋時代だったわけだ。
★古本初心時代
前にも書いたとおり自分の住む町にはまだ古本屋がなく、自動車雑誌以外にも読み始めた「ヒッチコックマガジン」や「宝石」のバックナンバーを少しずつ探すことを覚えてきた彼は、今はなき路面電車で三茶書房や江口書店を覗きに行くようになった。
中学校時代後期は彼の自動車趣味が最高潮に達した時で、雑誌「CARグラフィック」の創刊で外国車の魅力に取り憑かれて(もちろん国産車もだが)、当時ディーラーと呼ばれる販売店が集まった港区界隈を、学生ズボンにスニーカー姿でカタログの蒐集で徘徊したものだ。だから当時の子供としては珍しく町歩きになれてきていた。もちろん限られた区域には違いないが。
中学校を卒業するにあたって、当時としても数少なかった就職組に入って職についたものの、中学校時代の友人宅に遊びに行っても、高校に行ってしまった同級生はテストだテストだといって前のようには遊んでくれない。大人たちはエロ話しかしていないし。
つまらないので、高校に行ってみることにした。当時よく歩いていた地元の線路脇に、いつも生徒募集の立て看板が立っている公立の高等学校があったので、昼間は仕事を続けながらでも行かれるらしいので相談に行った。すぐにでも入れると思っていたら、年が明けてから試験を受けて入学するようにいわれた。
中学校時代、数学が嫌いで一桁台の点数しか取ったことがなく、試験は嫌だったが、薄い受験参考書をちょっと読んだりした。しかしそれで解るようになるほど数学は甘くなかった。定時制とはいえ、試験問題は全日制と同じもので、案の定、手も足も出なかった。だから、数学の答案用紙の裏にクジラのいたずら書きをして吹き出しにガオと書いて提出した。
もう受かる気はなかったが、取り敢えず発表を見に行ったら、やっぱり合格者と別に名前があった。職員室に来いといわれて、おそるおそる覗いたら教員たちから笑いがおこった。答案用紙の裏にマンガを書いた受験生は初めてだったらしい。ただ、他の教科がほとんど満点だったので総合で合格はしていたのだが、中学校からの書類が不備だという。不備も何も中学校へ受験の相談もしていなかったし、親にも言っていなかったのだから。出身中学はその高校とグラウンドを隔てた向こう側だったので、走って書類を取りに行った。
中学校の職員室でそのことを話したら、もう一度職員室中が爆笑に包まれた。取り敢えず担任の先生の祝福と一緒に書類をもらって、その日のうちに入学できたのだが。
教科自体は、地方の就職クラス(昔はそう言うクラス分けがあった)出身の学力に合わせたものだったので、いくら落第生とはいえ数学もやっとついていけるようになった。遊びのつもりで高校に入ったわけだから楽しくてしょうがなかった。
いくら定時制とはいえ、今思えば不思議なくらい自分と波長の合う教師がいて、生意気な小僧と遊んでくれたものだった。
コクトーの「阿片」や当時珍しいデモノロジーのルポだったバルネー「悪魔への祈り」をどうだと貸してくれた国語の教師を始めとして。
入学と同時に残業のない仕事に変わって、さらに幸運だったのは、新しい職場でお得意の集金を任されるようになって、月末には平日の昼間に都内を歩けるようになった。さらに本社が秋葉原で、途中で神田へ寄れるようになった。
もちろん十分な時間が取れるはずもないが、ある日一冊の本と出会う。神田八木書店のタグの貼られた、奥付に1964.6.10発行とあるその本はたびたびの蔵書の整理にもかかわらず40年近くたった今でも手元にある。
コスモグラフィア ファンタスティカという副題のついたその本は、ただの本好きだった少年を大きく変えることになった。当時ほとんど無名だったM.C.エッシャーの奇妙な表紙と我が魔道の先達という稲垣足穂への献辞は少年をその魔道に引きずり込んでしまったのである。
さらに、著者紹介で知った「黒魔術の手帖」「毒薬の手帖」は例の駅前の暗い小さな本屋で取り寄せてもらった。黒い貼り箱に入った真っ黒な布装のその本は、本が読むだけの存在ではないことを初めてその少年に教えてくれた。
(続く)